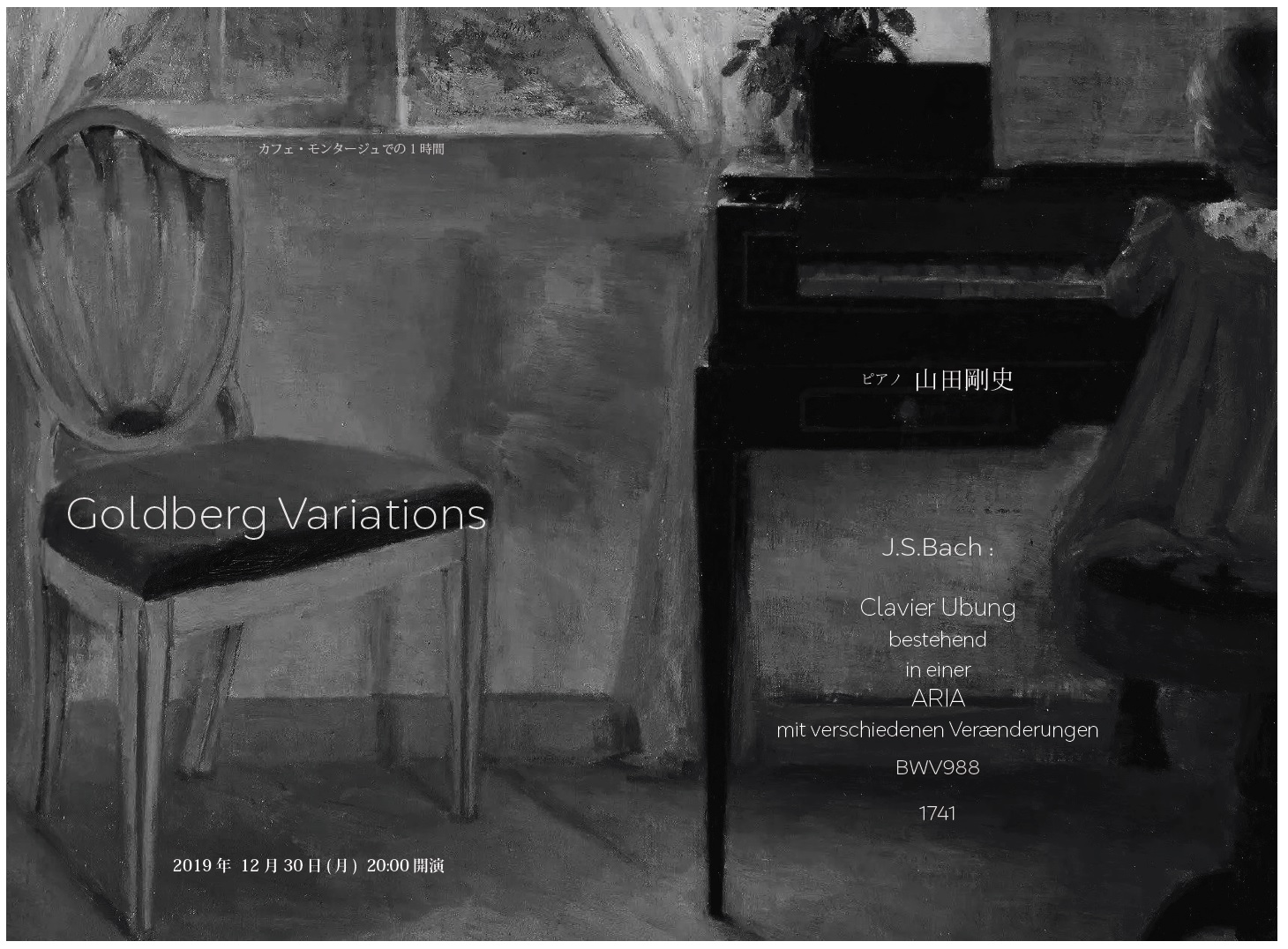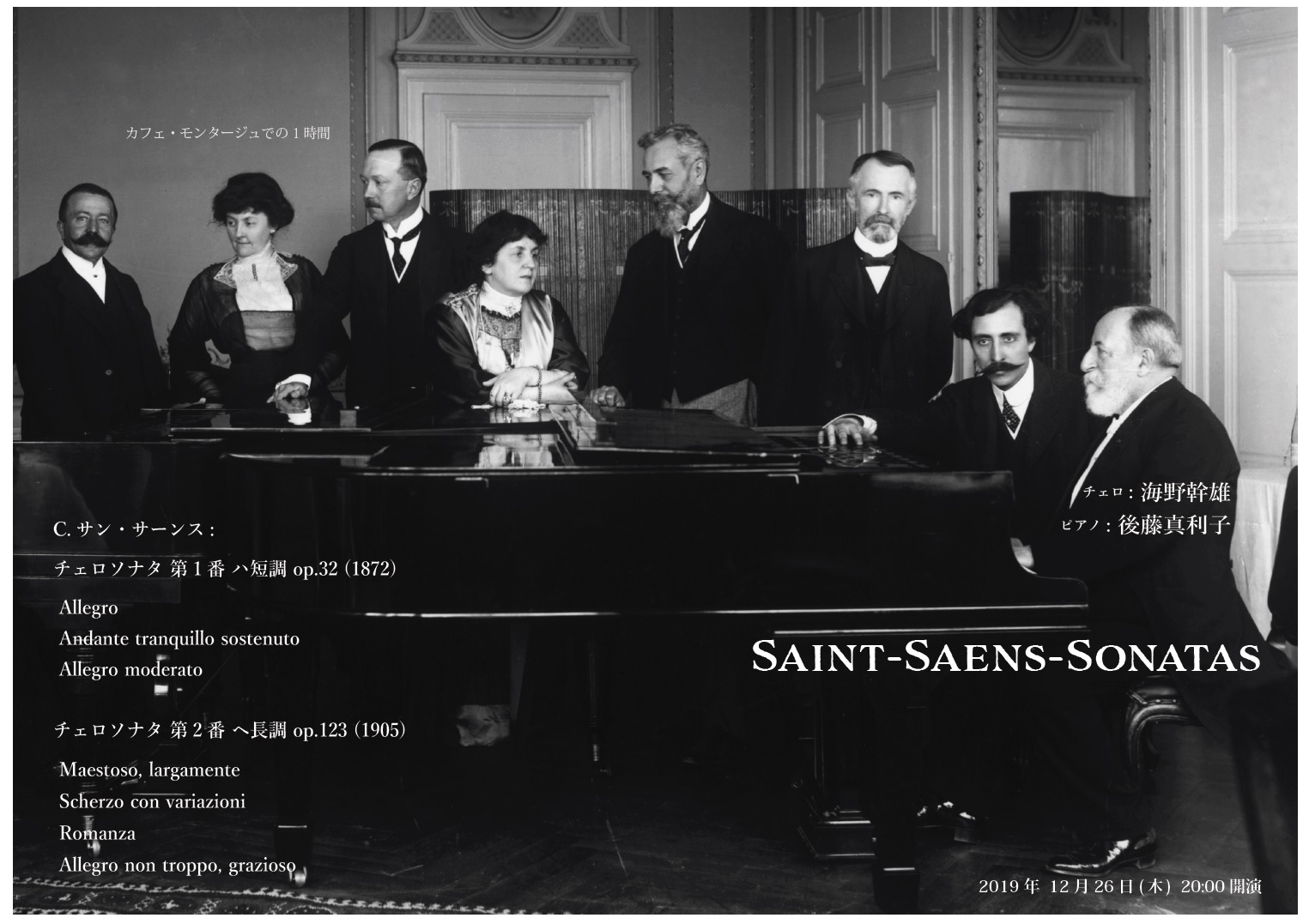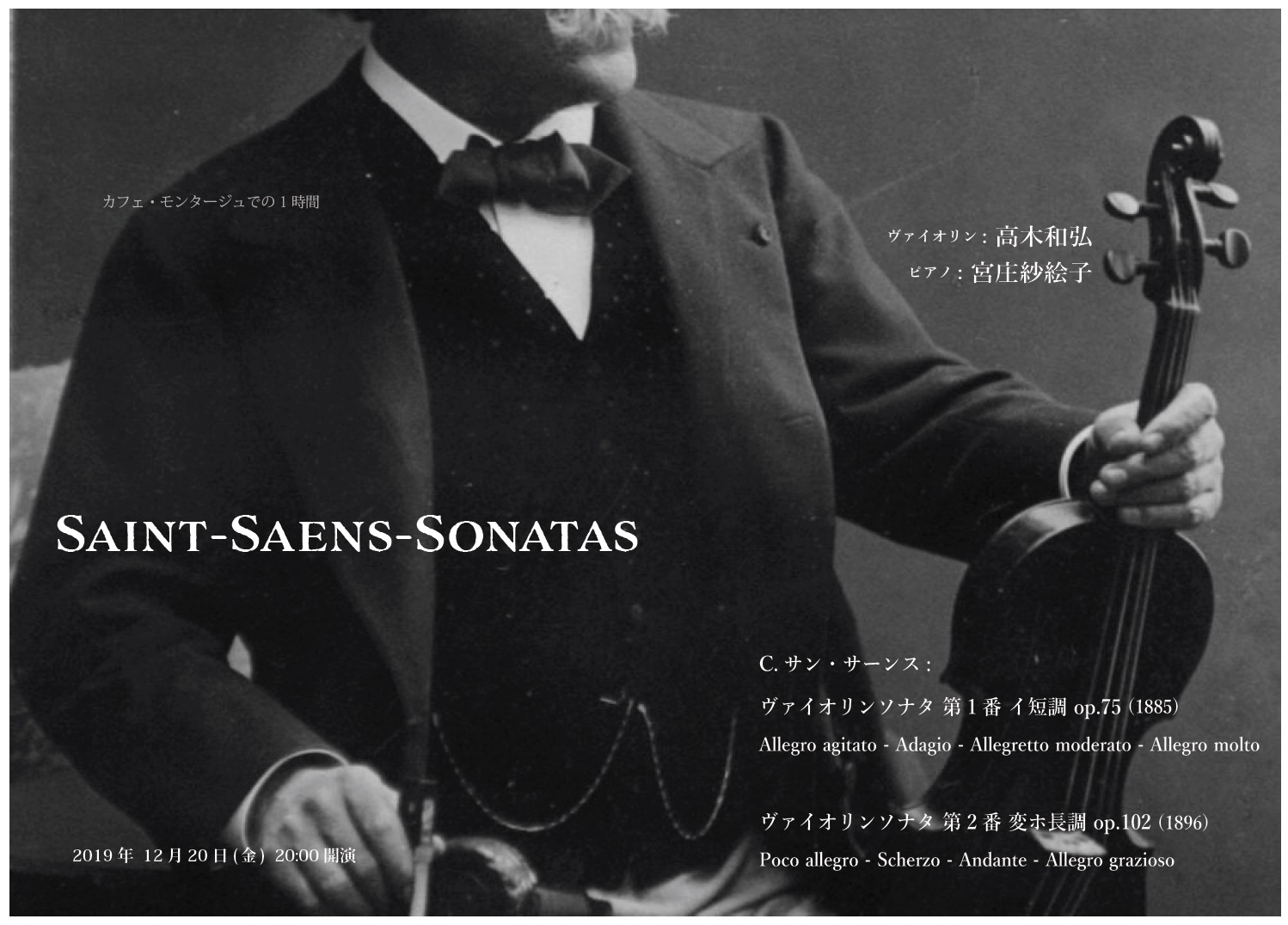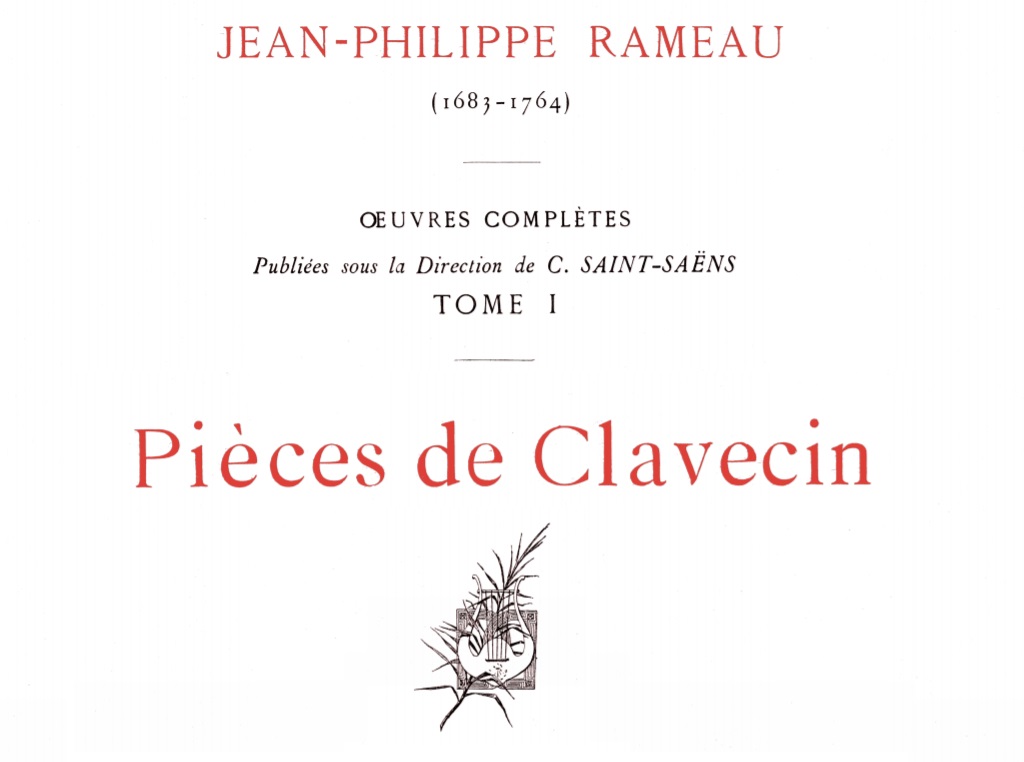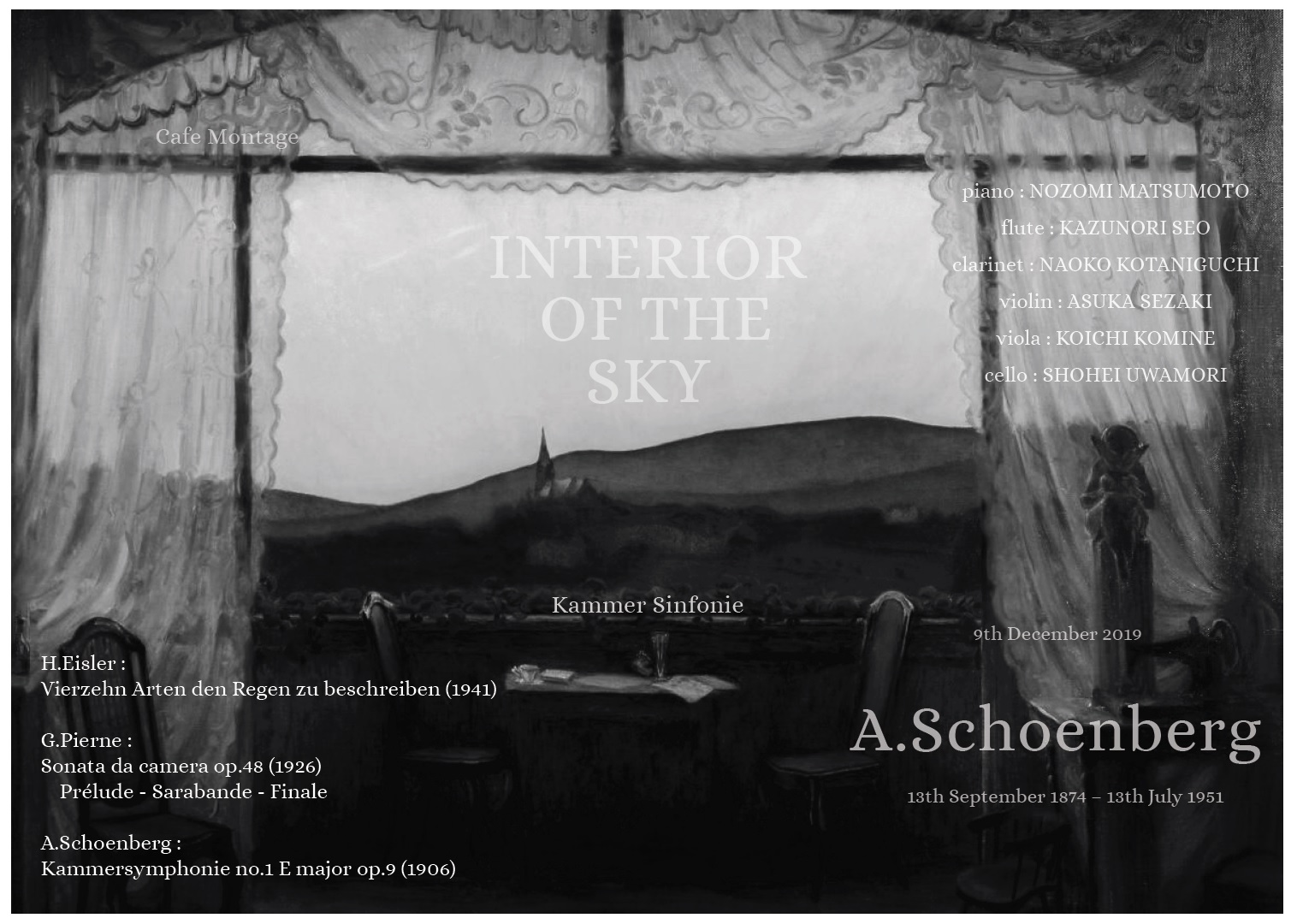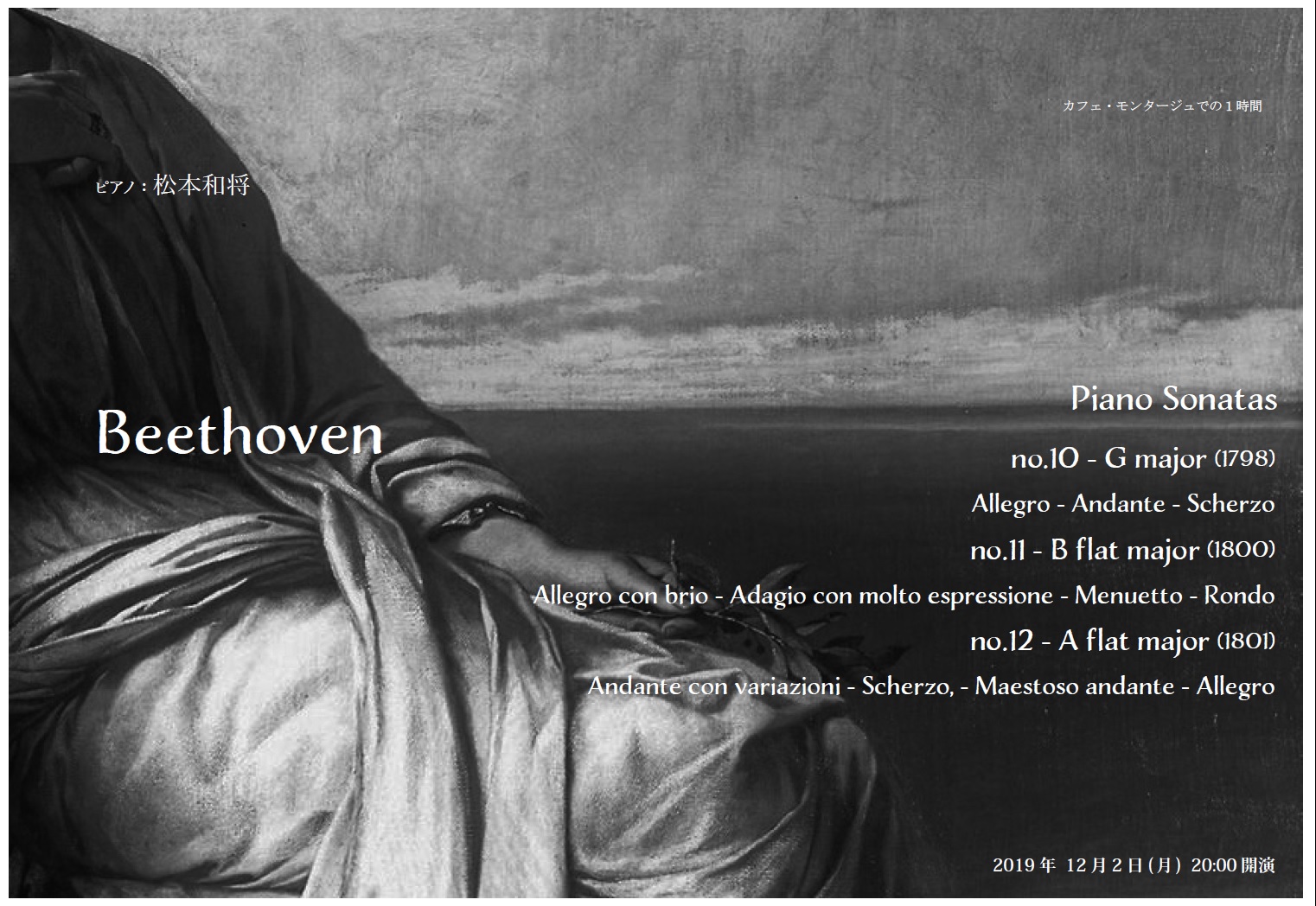アリア、とはなんだろう。
J.S.バッハが書いた一つの長大な変奏曲が1741年に出版された、その初版楽譜の扉には以下のように書かれている。
Clavier Ubung (- 鍵盤練習曲)
bestehend (- によって成り立つ)
in einer (- あるひとつの)
ARIA (- アリア)
mit verschiedenen Verænderungen (- それぞれ異なる変奏と)
日本語を並べ替えると
「ある一つのARIAと異なる変奏によって成り立つ鍵盤練習曲」
となる。 “ゴルトベルク変奏曲 目を閉じるアリア ” の続きを読む