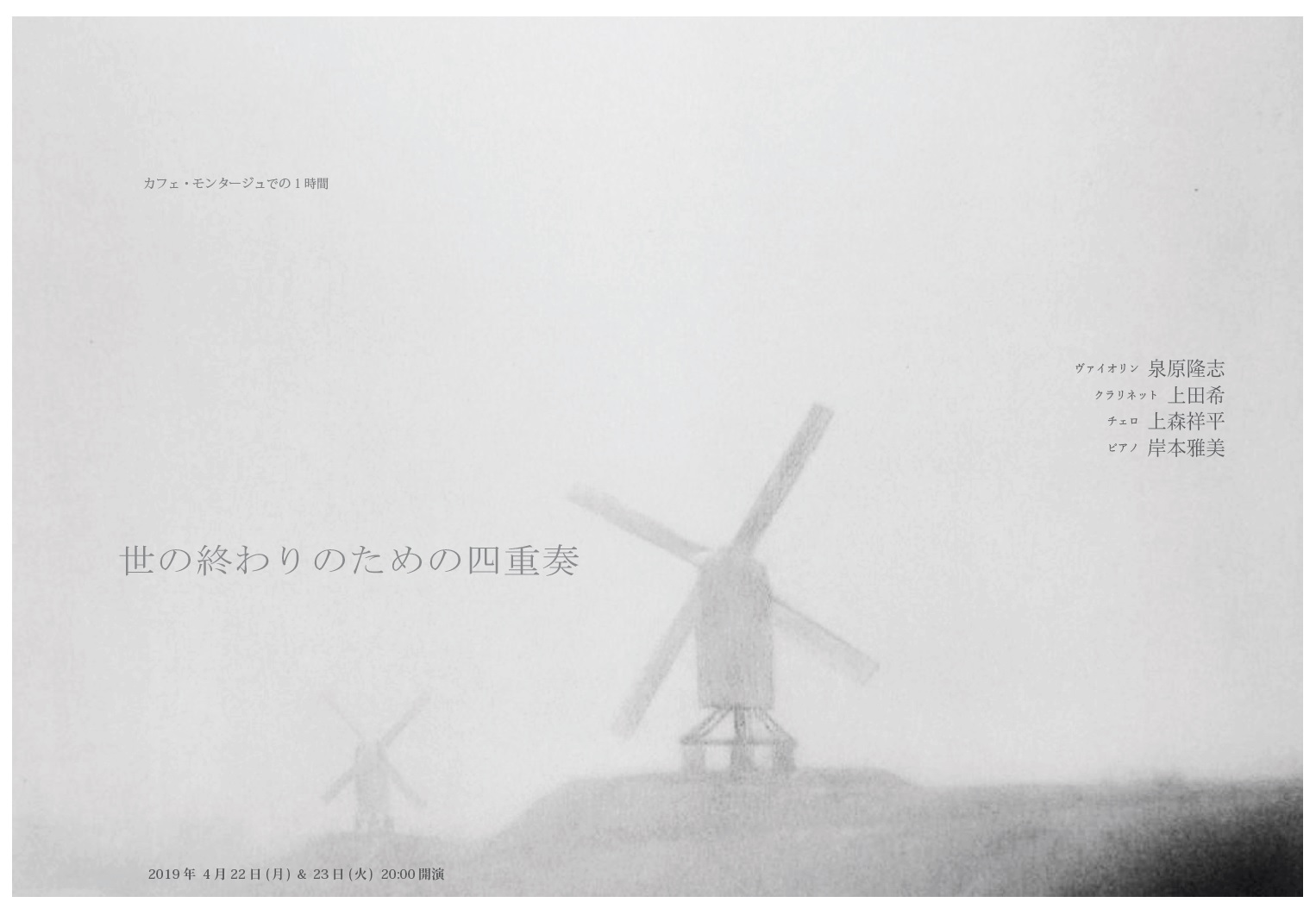ブラックホールの撮影に成功した、ということであった。
そこには「事象の地平線」という、極端に詩的な、ひとつの言葉が置かれていた。
27歳で戦死した詩人ミルモンの遺作による歌曲集『幻想の水平線』を思い出した。フォーレの最晩年、1921年の作品である。
船がすべて出払った港に、一人たたずむ詩人の叫び。
「私にお前たちの魂を繋ぎとめることは出来ない。
お前たちには私の知らない、はるか遠い世界が必要なのだ。」
光が抜け出すことのできない巨大な重量、引力が存在する。
ナポレオンの内務大臣を経て、元老院の議員となったラプラスはかつてそのように予言をしていた。存在するすべての粒子の動きを把握した知性は、人間も含めたすべての事象を予言することができるというラプラスの思想は、初めは「ラプラスの霊」と言われ、のちに「ラプラスの悪魔」と呼ばれるようになった。
モーツァルトは長く「ラプラスの悪魔」として扱われてきた。
ロマン派以降、モーツァルトが予言していたことの外に出ようという音楽の試みが様々に行われ、使える船は全て出航してしまったようだ。しかし、詩人は港にとどまっていた。
数学も音楽も言語であり、その最高の技法は「エレガントなもの」と形容されていた。
真理を映し出す公式であっても、その世においてエレガントでないものについては、記述がためらわれたという伝説の数学者が抱えていた葛藤は、そのまま芸術の歴史でもあった。
まず予言の形で記述されたものを、後に続いた者たちが数代にわたって観察、解釈していく。そこに発生する多数の誤謬もすべて、将来のエレガンスに寄与するものとして受け継がれていく。その中で生活する者は、自分の人生と過去に生きられたある人生の両方を生きていくことになる。
いずれは宇宙の神秘を解き明かす公式として現れるまでの、いわば大きな観察者としての青春時代を体験し、その中で幾度も滅びつつも、一度生きられた人生は完全に消え失せることがない。そのような宇宙的な時間は、芸術においても見出されたはずのものではなかっただろうか。
数学界のメンデルスゾーン、アーベルの画期的な論文について、それを誰よりも理解したであろう数学の巨人カール・フリードリヒ・ガウスは反応を示さなかったらしい。ガウスの後継者、ディリクレはフェリックス・メンデルスゾーンの妹レベッカと結婚した。
ディリクレの生徒であったリーマンの新しい幾何学とは別の筋道で非ユークリッド幾何学をまとめ上げたロバチェフスキーは、その晩年にウリヤノフという若く優秀な同僚を見出した。ウリヤノフの次男ウラジーミルはマルクスの著書を読み漁り、のちにレーニンという名前でロシアの十月革命を牽引した。その革命で故郷が失われたという失望のもと、ラフマニノフがロシアを去った。
20世紀のはじめ ロマン派の終結とともに芸術は終わった。
国家という思想の台頭、国境を公式として明らかにする中で、時間はそこに止まろうとしていた。ハプスブルクの終焉が戦争開始の合図であり、それが終わりの始まりであることが明らかになるにつれ、国家成立の公式はそのエレガンスを無視して動き出し、芸術もその成立定義から逸脱しようとしていた。
のちにアメリカに亡命したトーマス・マンが「私のいるところがドイツ」と発言したような、幾通りにも解釈された芸術の命題は、音楽においても「作曲家の作ったものが音楽である」という定義を通り越した無政府主義をも巻き込み、詩人はノスタルジーと未来の狭間の真空に取り残され、真空地帯は広がる一方となっていた。
曰く相対的に。
科学がその観察者の事情をも取り込んで観察されるに及んで、音楽もその聴衆の事情を取り込んで聴かれるようになった。
はるか昔、世界は静かであった。
単純な音響から発展した末に、音楽はついに全ての方向を指し示したノイズに帰するとしたイタリア未来派は、ファシズムの台頭に積極的に参加し、そこでもじっとしていることが出来ずに極端なアナーキズムを唱え始めて、ファシズムからも追い出された。
極めて高度な数学の公式を、そのままの形で読むことが出来る人がいるように、楽譜を音、つまり空気の振動に置き換えずにそのまま読むことが出来る人がいると仮定すれば、そこには「ラプラスの悪魔」が存在することになる。モーリス・ラヴェルはおそらくそれに限りなく近い人であった。
第一次大戦の終結において、自分を生み出した母という存在をあらゆる意味で失ったラヴェルは『クープランの墓』を書き上げ、1918年にそれが印刷されたすぐあと、出版社デュランに宛てて「何の意欲も、インスピレーションも到来しない。私は最悪の時間を過ごした」と書き送っている。
1920年、ラヴェルは『ラ・ヴァルス』の中にウィーンの空気振動を溶かし込んだあと、パリを去って「ベルヴェデーレ」という、ハプスブルクの離宮と同じ名前が付けられた屋敷に移り住んだ。そこで長期間に渡って書かれたヴァイオリンソナタのブルース楽章の中にはモーツァルトの有名な行進曲が溶かし込まれている。
ラヴェルはヴァイオリンソナタを仕上げるのに4年の歳月をかけ、結局それが彼の最後の室内楽作品となった。その間、バルトークのヴァイオリンソナタに刺激されて作曲した『ツィガーヌ』のパリ初演の前に、フォーレが死んだ。ラヴェルはピエルネ、ルーセルと共にベル・エポックを形作った世代の最後の生き残りとなった。
1931年、ドイツのナチス党の台頭とその社会における意味が想像を絶するものと確信していたヘルマン・ヘッセは、最後の長編小説となる『ガラス玉演戯』の執筆を始めた。2+2の答えを国家に委ねるようになってはいけないと警鈴を鳴らし、全てを投げうって彼を待つ魔の山へと向かった。
1933年2月8日、ラヴェルは友人の歌手マドレーヌ・グレイに「ファシズムの法則について、私達は考えが及んでいなかったね。」と書き送っている。その月末、国会議事堂放火を機にナチスは反乱の鎮圧を名目にして極端な行動をとりはじめた。スイスで講演をしていたトーマス・マンはそのままドイツに帰らなかった。
ほどなくしてドイツに最初の強制収容所が作られた。この年にボレロを指揮したのが、ラヴェルのパリでの最後のコンサートとなった。ラヴェルは、ナチスに都市を追われた芸術家たちを積極的にヴェルヴェデーレに迎え入れて、助けを施していた。
1937年「近代生活における芸術と技術」をテーマとしたパリ万国博覧会が開催された。その中でまずピエルネ、そしてルーセルが死んだ。メシアンは博覧会の「水の祭典」のために電子楽器の音楽を作曲した。博覧会の終了後にラヴェルが死んだ。
1940年 アメリカに渡っていたトーマス・マンはBBCを通じてドイツに流されるラジオ番組を、月に一度制作して「ナチスはドイツではない」と言い続けた。ドイツ軍の捕虜となっていたメシアンは収容所内で仲間たちと演奏するべく『世の終わりのための四重奏曲』を書いた。その中心にあたるイエスの永遠性についての楽章に、メシアンは1937年に書いた水の音楽を響かせた。
「戦争とは、口では文明のために遂行するものだというのだが、つねに文明からの休暇であり、だから愉快なのだ。」
1944年2月のトーマス・マンの寄稿文「世界の安全保障は可能か」の中には、おそらくはルーズベルトに近いところで、来るべきドイツの運命、そして戦争の終結までのシナリオを知ってしまい、全てがもう取り返しのつかない段階にあることへの絶望と怒りそして諦念が押し寄せ、溢れかえっている様が見える。
「…将来へのあらゆる見通しから判断して、最終的に戦争を阻止する決め手となりうるのは道徳と理性ではなく、物理学であろう。今日すでに技術は全体戦争の手に、全体戦争の存続を危うくし始めている破壊手段をゆだねつつある。耳にするありとあらゆる情報によれば、ウラン原子力を開放すれば、どんな冗談も終りになるだろう。そして、どうやら人類は戦争を克服できない前に、戦争をあきらめねばならないだろう。が、これは人間愛の見地から見れば遺憾な事である」
ヘルマン・ヘッセが10年間にわたって書き上げた『ガラス玉演戯』がトーマス・マンのもとに届けられたのは、この寄稿文を書いたすぐ後の事であった。第14章まで書き進めていた『ファウスト博士』の着想と重要な部分で重なりあうヘッセの大作を前に、マンは震えていた。
「自分はこの世に一人でいるわけではない」
1945年3月、ヒトラーが姿を消した。ベルリンは陥落間近。3月25日、トーマス・マンはラヴェルの『ラ・ヴァルス』を初めて聴いて震撼していた。いずれウィーンも陥落する。
最悪のシナリオが予想される中でも、この人物であれば自分の意思を委ねたことに後悔はないとトーマス・マンが考えていたその人、フランクリン・ルーズベルトが1945年4月12日に急死した。
1945年8月6日、トーマス・マンの日記
「分裂させられた原子の力が作用する爆弾がはじめて、日本への攻撃に使われる。かくして秘密は明るみに出た。― もしかするとドイツ人の援助があったのかもしれない。数多くのドイツ人物理学者が今アメリカで働いているという事だから ―ヒトラーのドイツのためのするのと同じ誠意をもって。原子爆弾は二十億ドルかかった。そして何万もの人が極秘の分業体制でそれに従事した…」
終戦から1年以上後、1947年1月にトーマス・マンは『ファウスト博士』を書き上げた。
日本の戦後が終わろうとしている今、
「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに 心から安堵」
という会見の声が聞こえた。
私は戦争を知らない。
戦争の意味も、もう誰も戦争を知るものがいないということの意味も、私はまだ知らないのだ。
『ガラス玉演戯』の主人公も、『ファウスト博士』の主人公も、時間が終わってからずっと静かなままで、今を迎えている。
・・・・・
2019年4月22日(月)&23日(火)
「世の終わりのための四重奏」
ヴァイオリン: 泉原隆志
クラリネット: 上田希
チェロ: 上森祥平
ピアノ: 岸本雅美
http://www.cafe-montage.com/prg/19042223.html