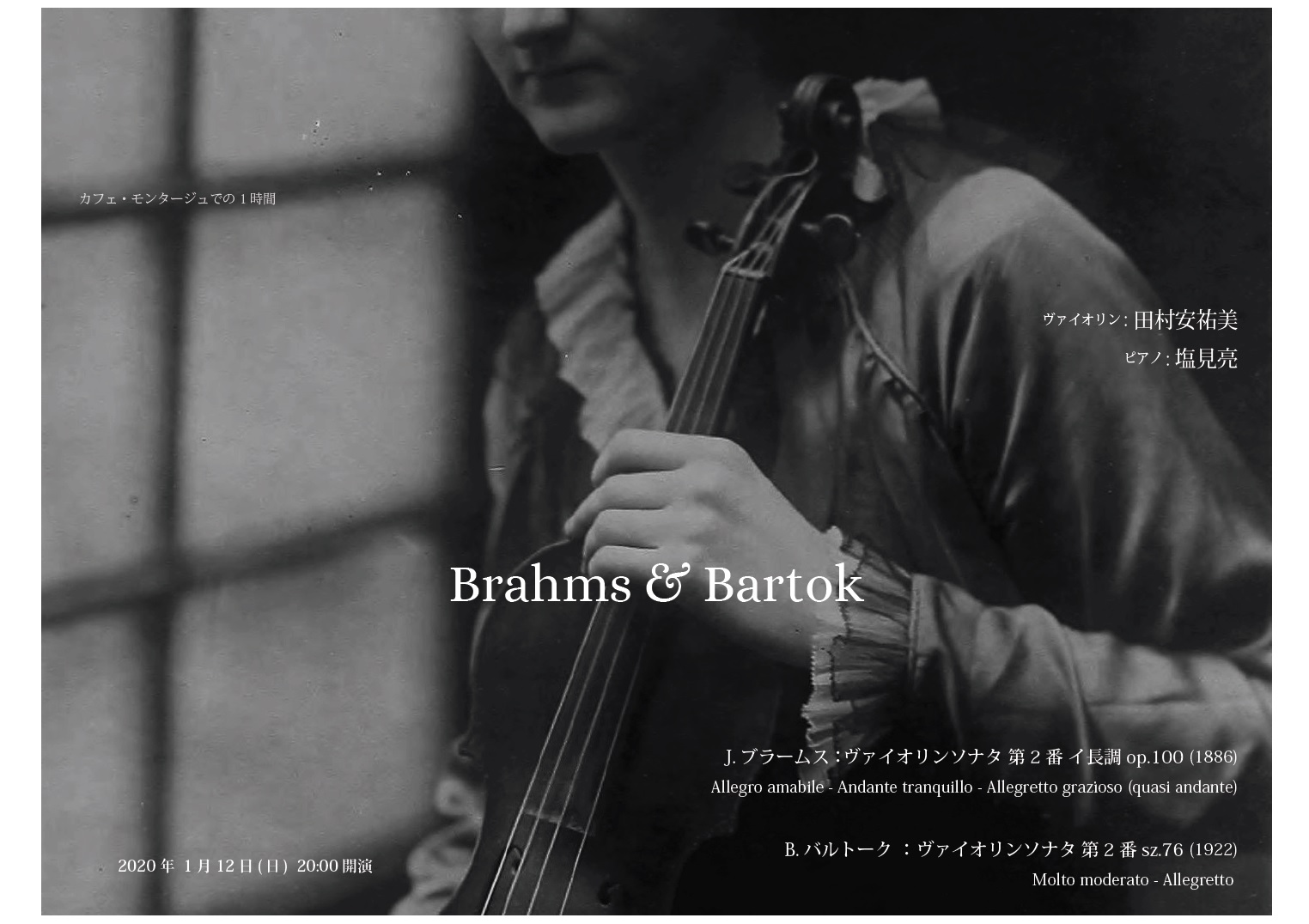第一次大戦がおわってまもなく、バルトークの音楽は急激に世間から賞賛を得ることになった。それまで孤独を極めていたバルトークは喜んだ。
しかし、彼はすぐに塞ぎ込むのだった。
民謡を採取しての旋律の研究がまだ中途のままであったのに、戦争で分断されたハンガリーの地方への道が閉ざされたままであったからである。それはバルトークにとっては未来への道をふさがれているのと同じことであった。
「音楽学のこの分野に対する真の関心は、世界のどこにも現われていません。このような現状を考えますと、民族音楽研究という音楽学のこの分野は、それにとりつかれている数人のものにとってのみ重要なことで、それ以外のものにとってはまったくとるに足らないことである、ということはありえないことではありません!」(バルトーク – 1923年)
1907年、パリから帰国したコダーイに教えてもらったドビュッシーの音楽の中で、バルトークが第一に評価したのは音響の効果ではなくその東洋風の旋律であった。そのことはバルトークがロマン派から急激に離れる大きなきっかけともなった。
バルトークは、ストラヴィンスキーの作品の中に聴こえる民謡の旋律が作曲家自身によって採取されたものではないこと、そして各々の「主題の出典をけっして明かさない」ことが本質的にモリエールの主張と同じであり、ストラヴィンスキーが「古い時代の作曲家の習慣」に従っていると何度も発言している。
「彼ら(過去の大作曲家)も同様に、この種の情報について大抵、完全な沈黙を貫いた」とバルトークはいうのである。
バルトークはシェーンベルクの作品の古典性を称賛しながら、それが民謡の旋律を排除する方向に進んでいくことを確認した後、それが未来の音楽であることを保留していた。
バルトークは道を塞がれた地点から未来の音楽を作り出した。その先駆けとなったのが1921年と翌22年に続けて作曲されたヴァイオリンソナタ 第1番と第2番であり、それらはモーリス・ラヴェルのほか多くの作曲家を熱狂させ、その成功が後のピアノ協奏曲 第1番(1926)や弦楽四重奏曲 第3番(1927)へと進む方向を決定づけた。
旋律の出自を明らかにすることで、過去との決別を謳ういかなる先進的な音楽も過去との対話であるということを宣言し、それが「新古典」であると言い続けて、その度にバルトークは塞ぎ込んだ。
まだハンガリーが大きな国であったころ、ブラームスから受けた深い影響からはかけ離れたかに聴こえるバルトーク後期の作品の中に、そのような対話を聴くことが出来るのはまだこれからのことかも知れない。
・・・・
2020年1月12日(日) 20:00開演
「ヴァイオリンソナタ」
ヴァイオリン: 田村安祐美
ピアノ: 塩見亮
https://www.cafe-montage.com/prg/200112.html