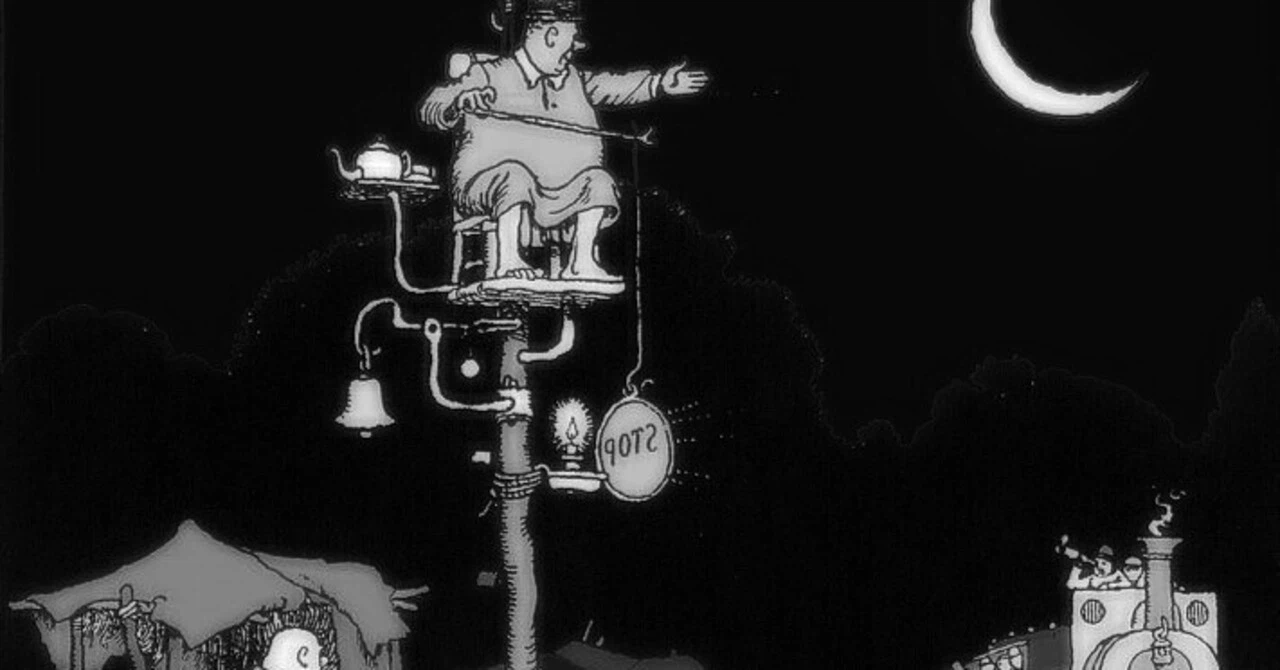全てのものが全ての人のためにあるわけではなく、
全ての人が全てのもののために生きているわけではない。
まさにそうでしかない、このような言葉をドヴォルザークはアメリカを去る直前に、プラハの自分の弟子に書き送っている。
ドヴォルザークがアメリカを去ったのは、彼が故郷を愛するゆえのホームシックからだといわれている。それも、まさにそうなのだろう。
しかし彼にとっての「ホーム」、つまり故郷とは何だったのか。
信仰深き人間としてのドヴォルザークの故郷はチェコであった。
そして、作曲家としてのドヴォルザークの故郷はブラームスであった。
二つの故郷は、はじめから相入れないものであった。
ブラームスは神を信じていない
ウィーンで初めてブラームスとの対面を果たしたドヴォルザークは、プラハに帰るやいなや、ヤナーチェクに向かってそう言ったのだという。
ブラームスはいつでもドヴォルザークを「素朴な天才」として扱おうとした。本当にそう思っていたかどうかはともかく、その方が人受けがよい事は確かであったようだ。
ドヴォルザークは働き過ぎで疑ったりする暇がなく、子供時代に教わったことに一生留まるのだ。
人々はそんなドヴォルザークを快く受け入れた。
クララ・シューマンにだけは通じなかったらしく、ブラームスはドヴォルザークの連弾曲をシューマン邸に持ち込んでクララと連弾をしながらドヴォルザークを気に入ってもらおうと労を惜しまなかったが、ロベルト・シューマンの妻であった人に「素朴さ」を売り込むのは無理な話だった。
ともかく、ブラームスはいつでもドヴォルザークが「素朴な働き者」であるがゆえに、「文学を読む時間がない」とか「音楽のことについても、知見を深める時間がない」といいながら、「でも、作品は素晴らしい」と繰り返し褒めたたえ、ドヴォルザークは快進撃を続けた。
推しを売り込む際に、先に「こういうところは確かに足りないのだけど」と留保する点をつくっておいてから「しかしながら」と持ち上げていくのがブラームスの流儀だ。
でも、当のドヴォルザークが本当に時間がなかったのか、それ故に音楽以外のことがおろそかになっていたのかと言えば、どうなのであろう。
ドヴォルザークはいわばブラームス・プロデュースの「チェコの作曲家」の役割をある程度受け入れていたようではあった。しかし、時代は急激に変化し、ドヴォルザークがアメリカに渡っていた1892年からの3年の間に、ブラームスは最後のピアノ作品とクラリネットソナタを書き、グスタフ・マーラーは交響曲 第2番「復活」を書き上げていた。
アメリカで忙しすぎたドヴォルザークはそうしたウィーンの音楽事情には通じていなかったであろうか?おそらくそうではない。
アメリカでその土地固有の音楽に触れたドヴォルザークは、いずこにも宿っている神の存在を意識せずに、子供のころの信仰のままに留まり続けていただろうか?おそらくそうではない。
ブラームスの元を訪れる前の若かりし時代、ドヴォルザークは「素朴なチェコの作曲家」ではなくワグネリアンであった。そして、チェコ伝承の音楽素材を扱った先達としてシューベルトを尊敬していた。つまり、神が唯一の存在ではない世界に、かつて彼は住んでいたことがあるのだ。
ドヴォルザークがアメリカから帰ろうとした「故郷」はどこなのだろうか。
1895年の始め、チェロ協奏曲を書き上げたドヴォルザークはアメリカを離れてチェコに帰った。そして、巨大な弦楽四重奏曲をシューベルトの最後の弦楽四重奏曲の調性であるト長調で書き始めた。
そこには「素朴なチェコの作曲家」が確かに立っている、笑顔を見せて。でも、そこにはワーグナーから譲り受けたかのような記憶のヴェールが幾重にも張り巡らされている。記憶の向こう、「素朴な」舞曲が無数のヴェールの背後で、様々な時間の流れにさらされているのが見える。
過去と未来の境目が段々にあいまいになって、ラヴェルのラ・ヴァルス、つまり世紀末ウィーンが消去に向かうのをドヴォルザークの大きな眼を通して見ているような、恍惚とした世界が前に後ろにと広がっていく。
ドヴォルザークはこの弦楽四重奏曲を書いた翌1896年に、4つの交響詩を書いた。
口承文学や民衆詩を採取しながら物語発生の源をたどり、いつの時代にもあり得た出来事として、果てしない未来をも予言する詩を書いたエルベンの書を元に、ドヴォルザークは音と時間だけの4つの物語を綴った。同じ年、マーラーは「子供の魔法の角笛」を元に交響曲 第3番を書き上げた。
翌1897年、ブラームスの死を境にドヴォルザークはオペラの作曲へと向かった。
忙しすぎる作曲家の役目を終え、ようやくドヴォルザークは彼自身の時間を手に入れたということなのだろうか。ドヴォルザークの晩年の全貌を自分はまだ見ることが出来ていない。
過去も未来もない、偉大な時間の終わりに書き残された巨大なト長調の弦楽四重奏曲。膨大な時間の奔流の先は果てしなく、故郷への道はどこまでも進んでいくようだ。
・・・・・
「新たなる出発」
Martinu & Dvorak 7 String Quartets – Vol.3
ヴァイオリン:杉江洋子
ヴァイオリン:野田明斗子
ヴィオラ:小峰航一
チェロ:ドナルド・リッチャー
https://www.cafe-montage.com/prg/230204.html