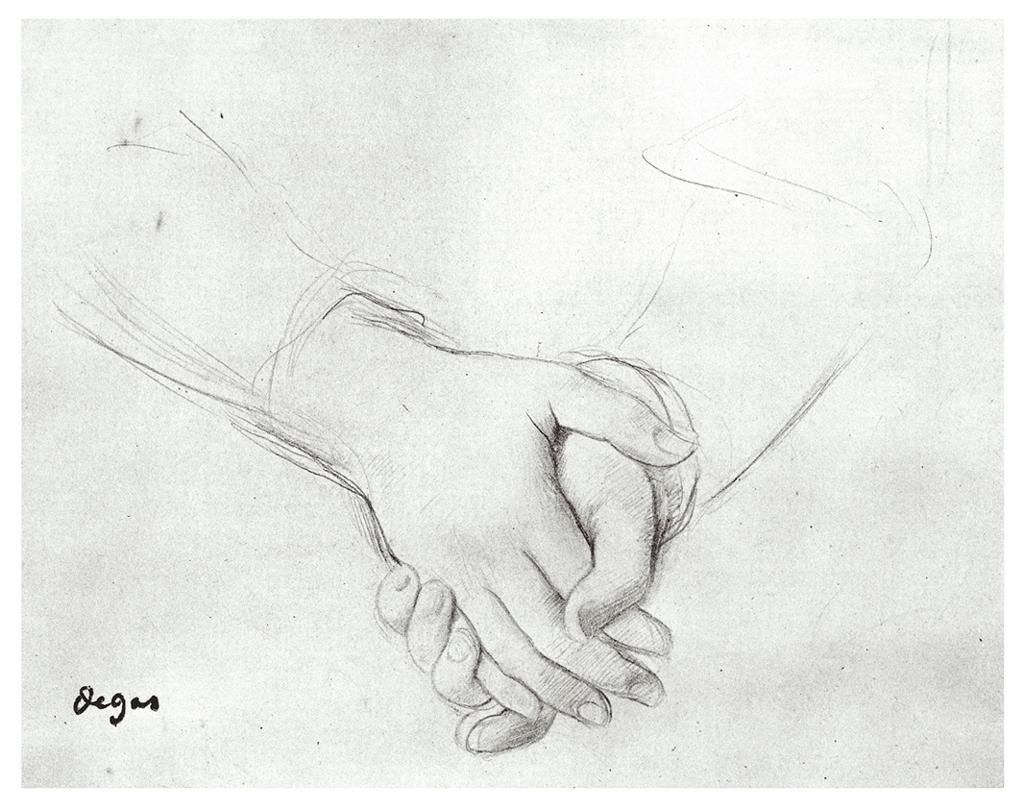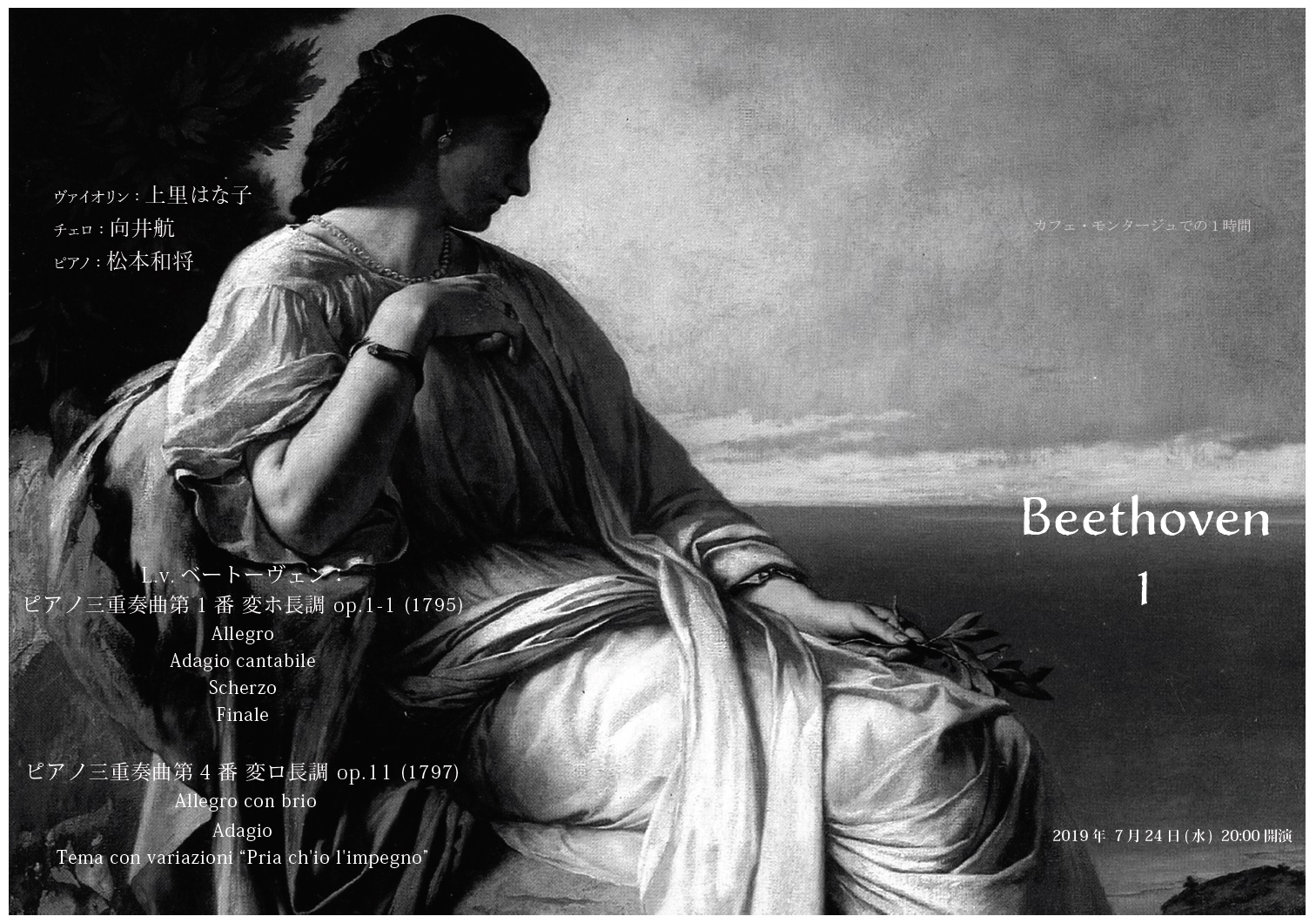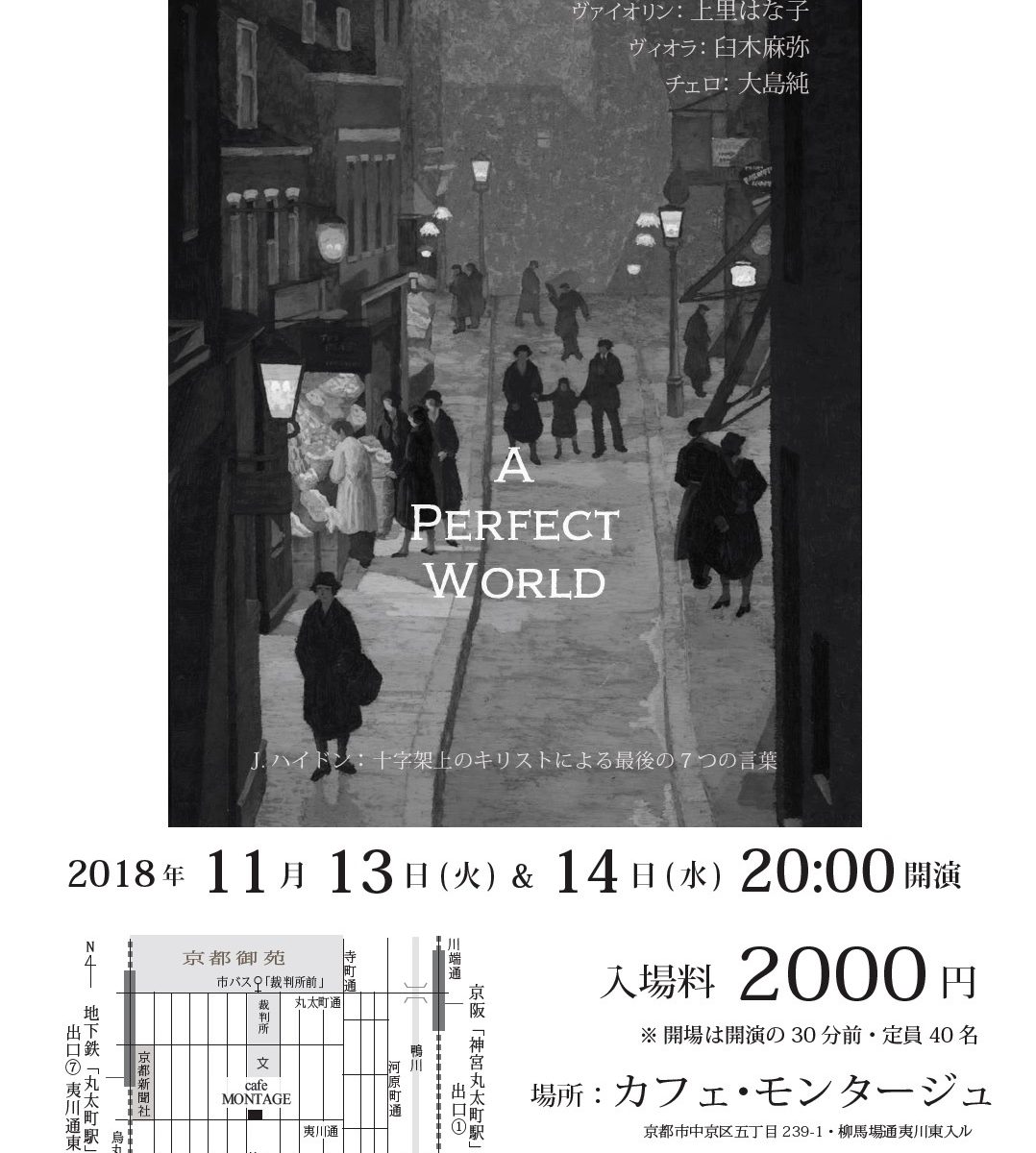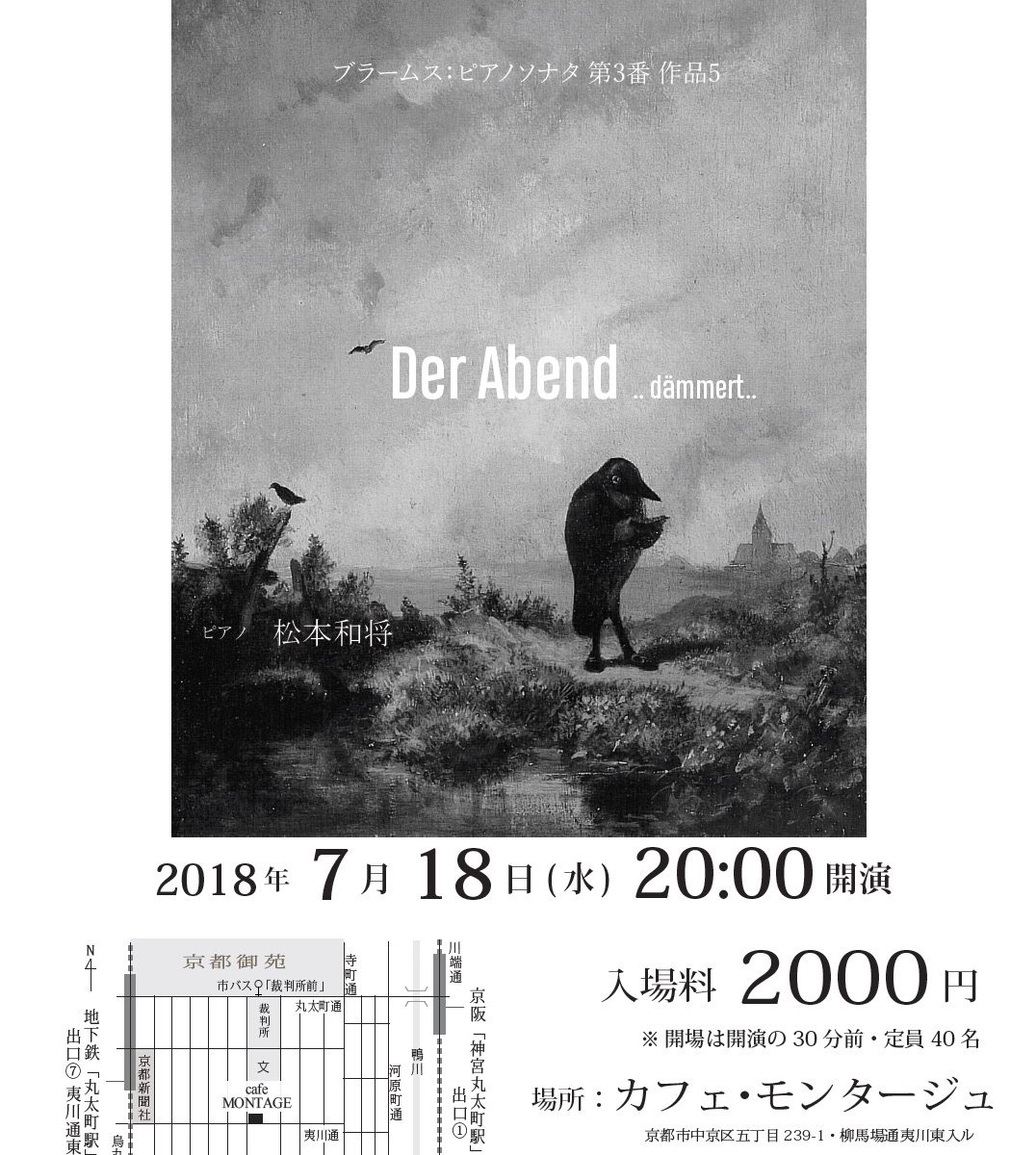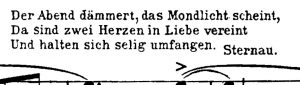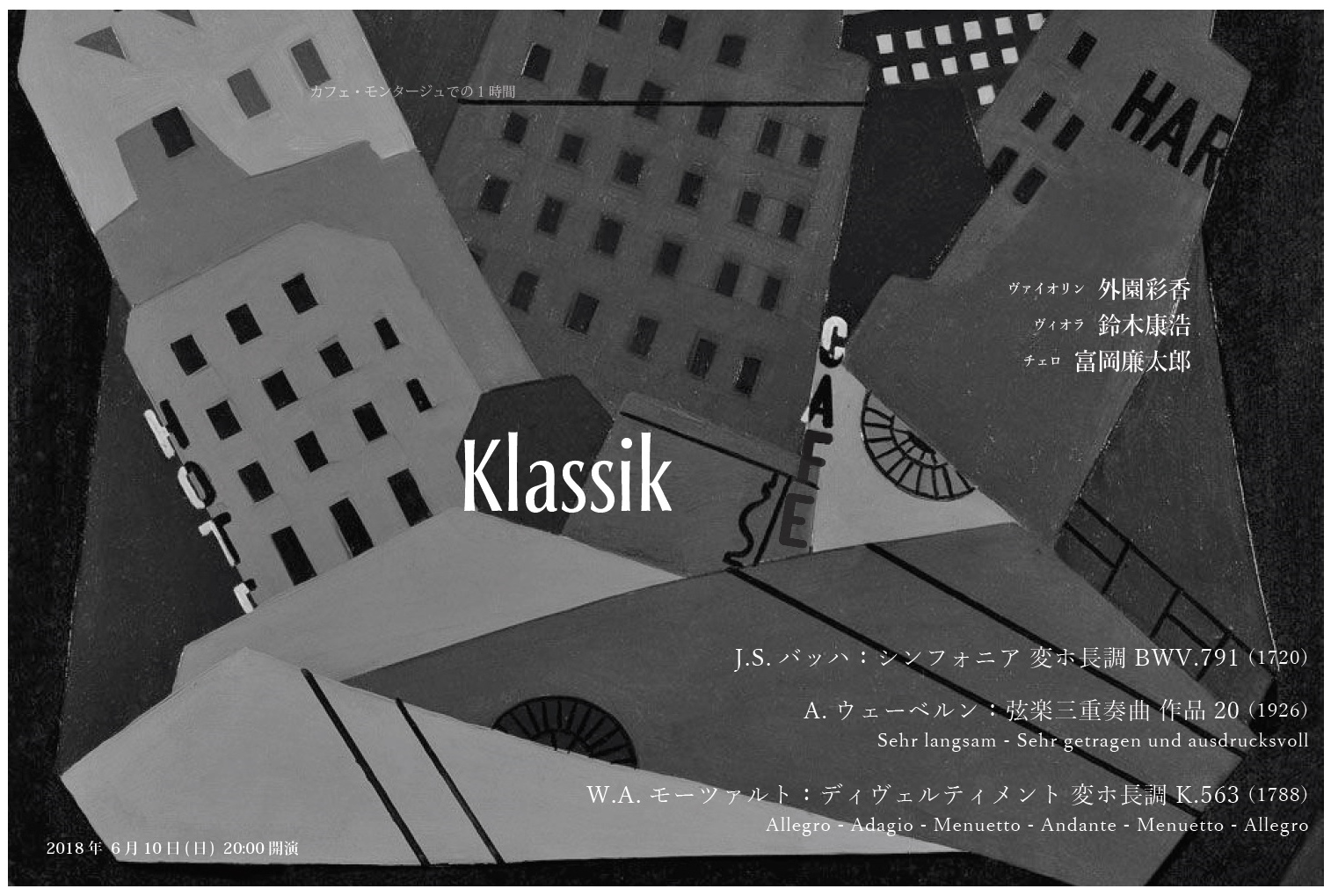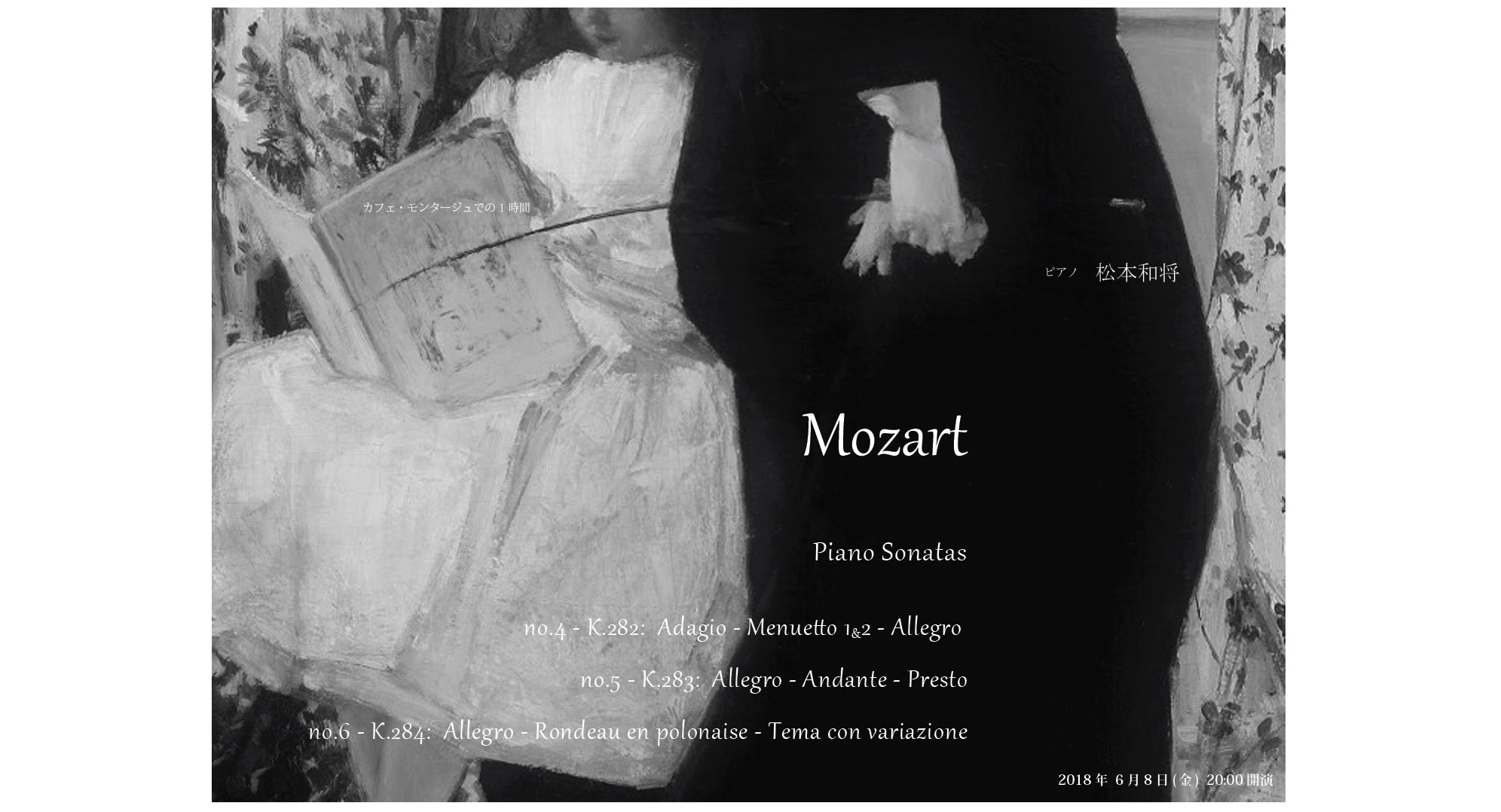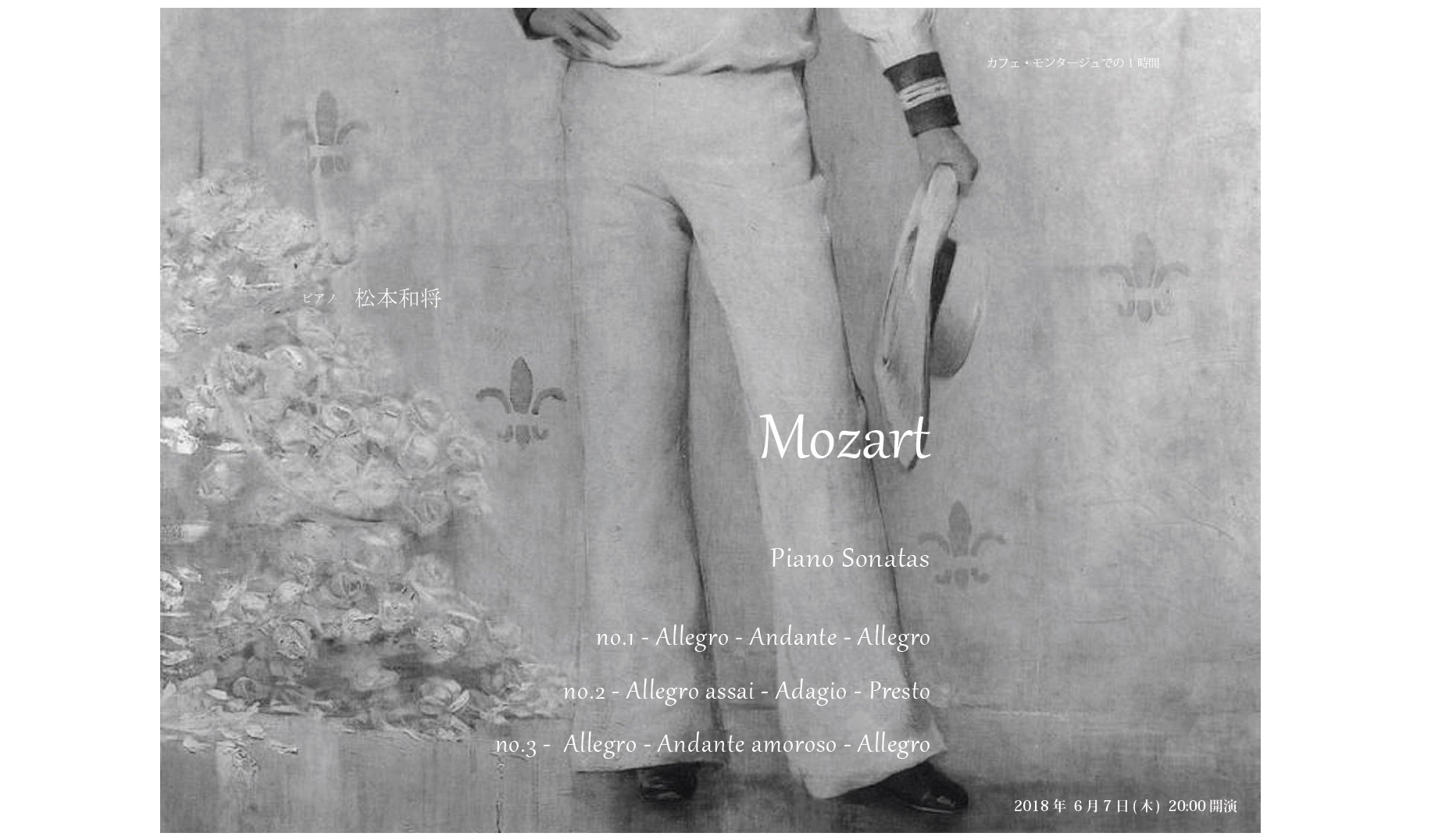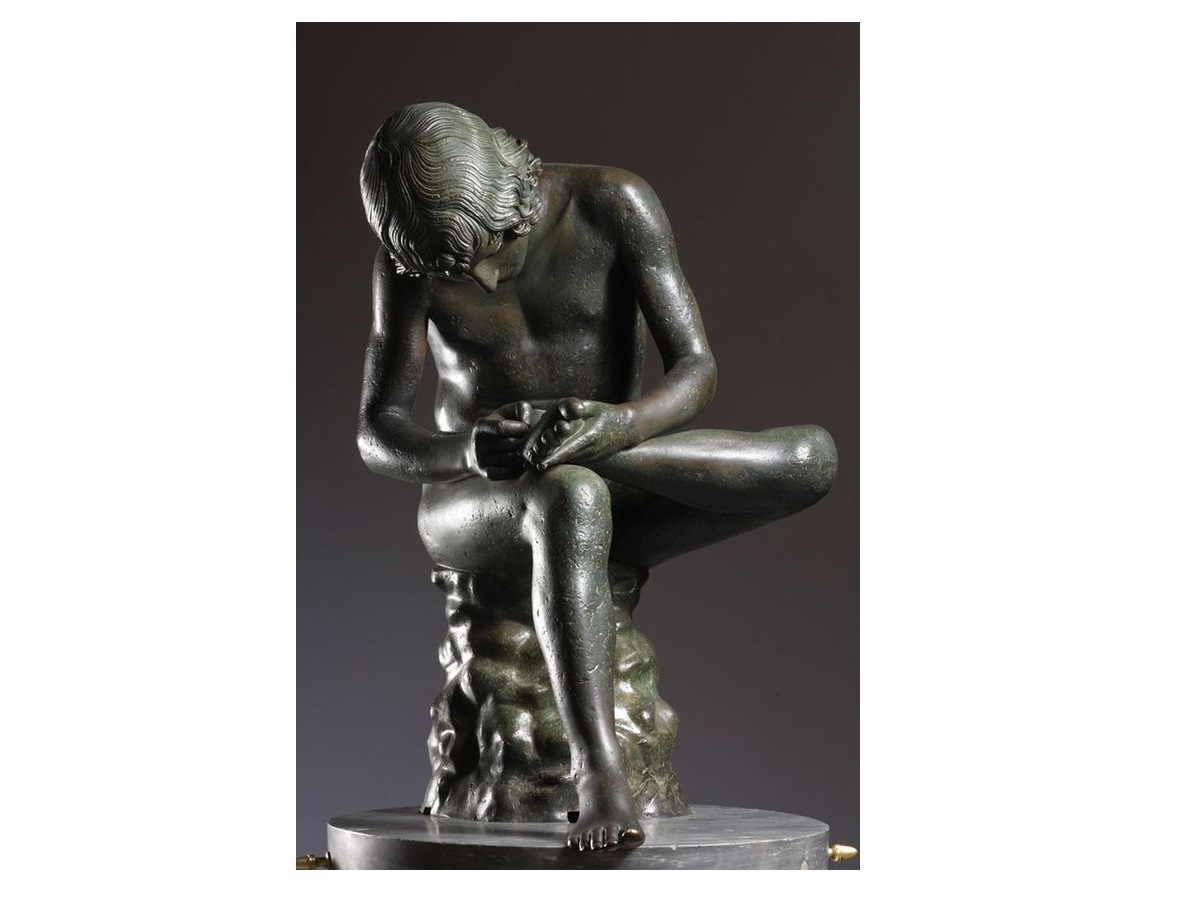1821年1月25日、シューベルトの作品がウィーンの楽友協会ではじめて聴かれた。ギムニヒの歌唱、ピアノはシューベルト自身(もしくはアンナ・フレーリヒ?)で作品は「魔王」であった。
同じ年にシューベルトはピアニストもしくはヴィオラ奏者として楽友協会に登録された。同じくピアニストとして登録のあったリーベンベルクと知り合ったのはこの頃のことではないかとされている。フンメルの弟子で腕の立ったリーベンベルクはピアノの作品を書いてくれないかとシューベルトに頼んだのであるが、その願いは果たして翌年にハ長調の「さすらい人幻想曲」として叶えられたのであった。
シューベルトが規模の大きなピアノソナタを3つ立て続けに書いたのは1828年、体調を悪くして友人ショーバーのところから兄フェルディナントの住居に居を移してすぐの9月のことであった。 “フンメルに捧ぐ” の続きを読む