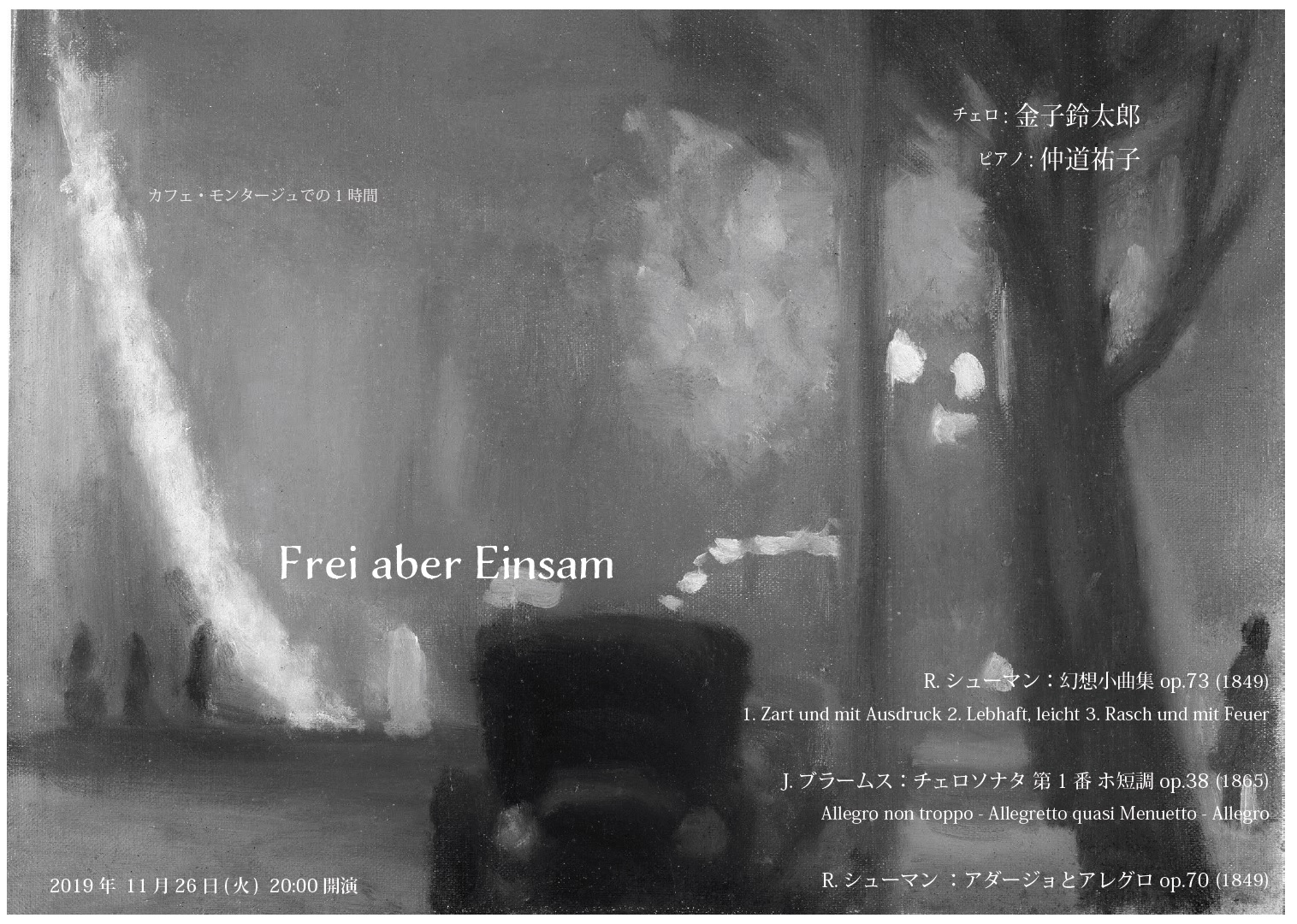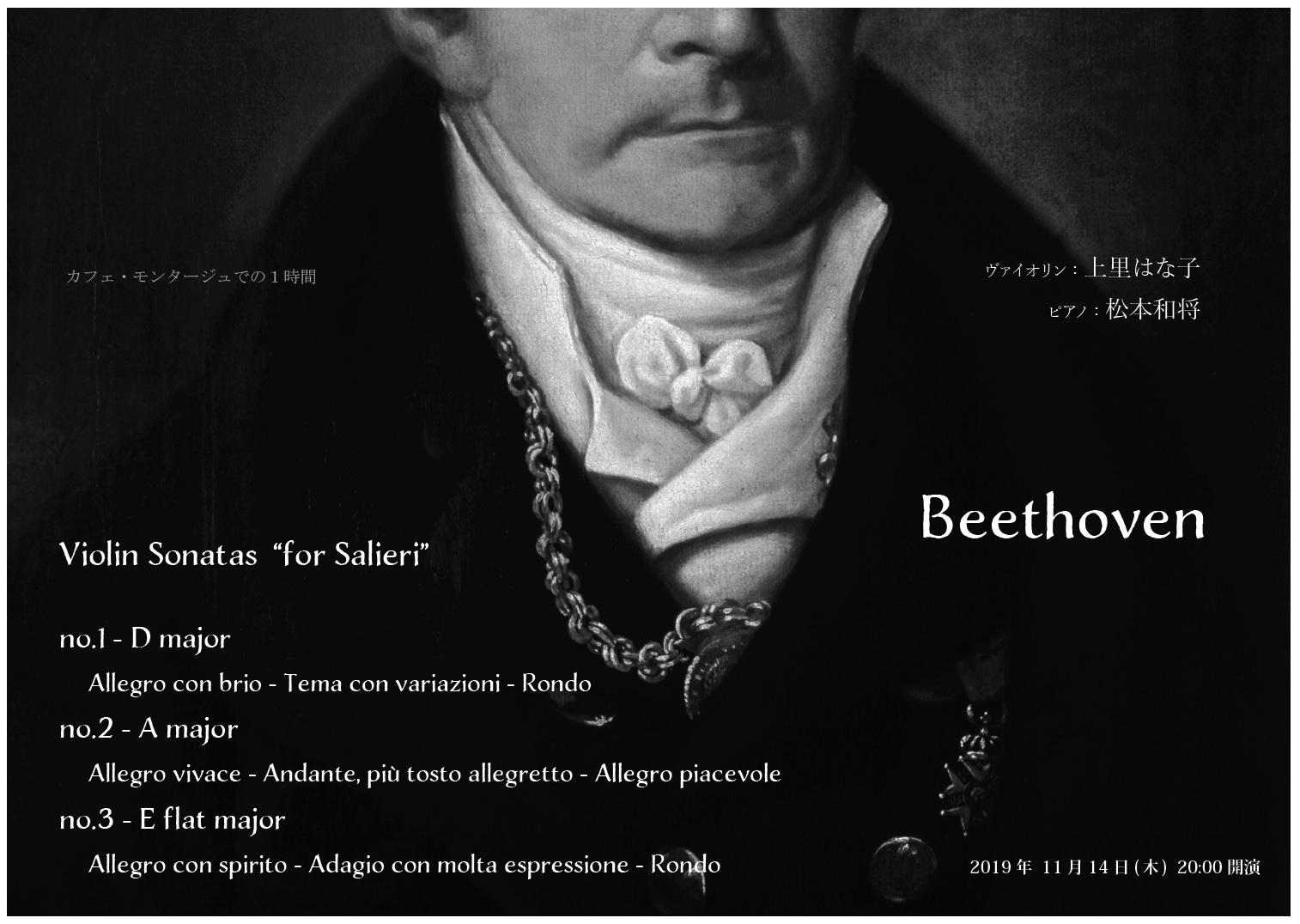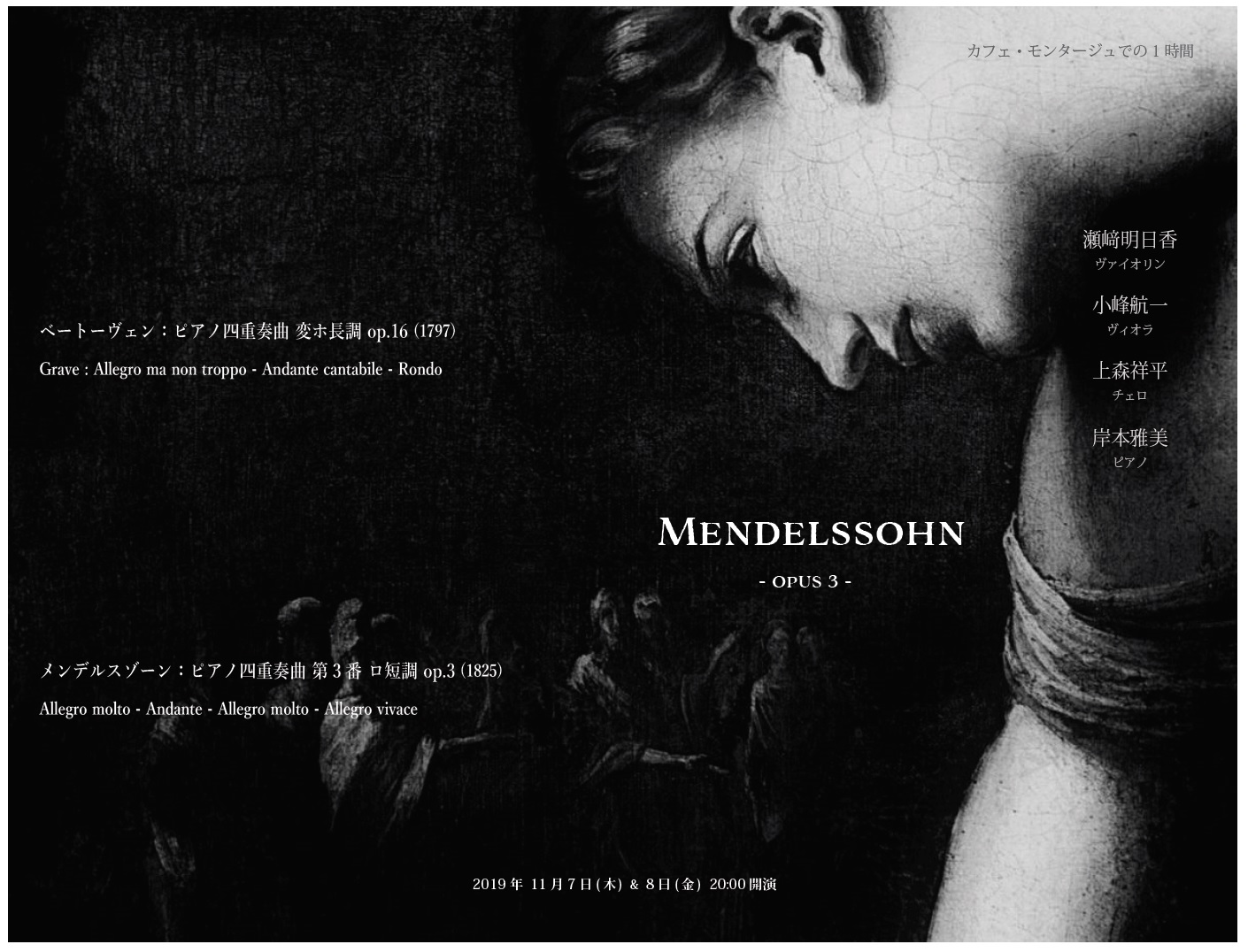ノッテボームというのは大変に偉い人で、ライプツィヒで学んでいたころメンデルスゾーンから見せてもらったベートーヴェンのスケッチ帳に魅了されて、ウィーンに引っ越しをして、まだ誰も手を付けていないベートーヴェンの自筆譜の研究に没頭した。
ベートーヴェンの作曲の過程については、弟子たちがなんとなく語った逸話よりほかに確かなものはなく、アメリカ人のセイヤーが初めての本格的な自伝を執筆していた時期、ノッテボームが始めた研究は今日の自筆譜研究の先駆となるものだった。
ノッテボームはサラミが好きで、いつも決まったお肉屋さんでサラミを切ってもらっていたのだが、ある日、お肉屋さんが渡してくれたサラミの包み紙に何か落書きがしてあるのに気がついた。よく見るとそれは五線譜に書かれた楽譜で、さらに目を凝らすと、どうやらそれはベートーヴェンの筆跡であると気が付いた。でもそれは、これまでに見たことのない作品であった。 “ウィーンのブラームス チェロソナタ 第1番” の続きを読む