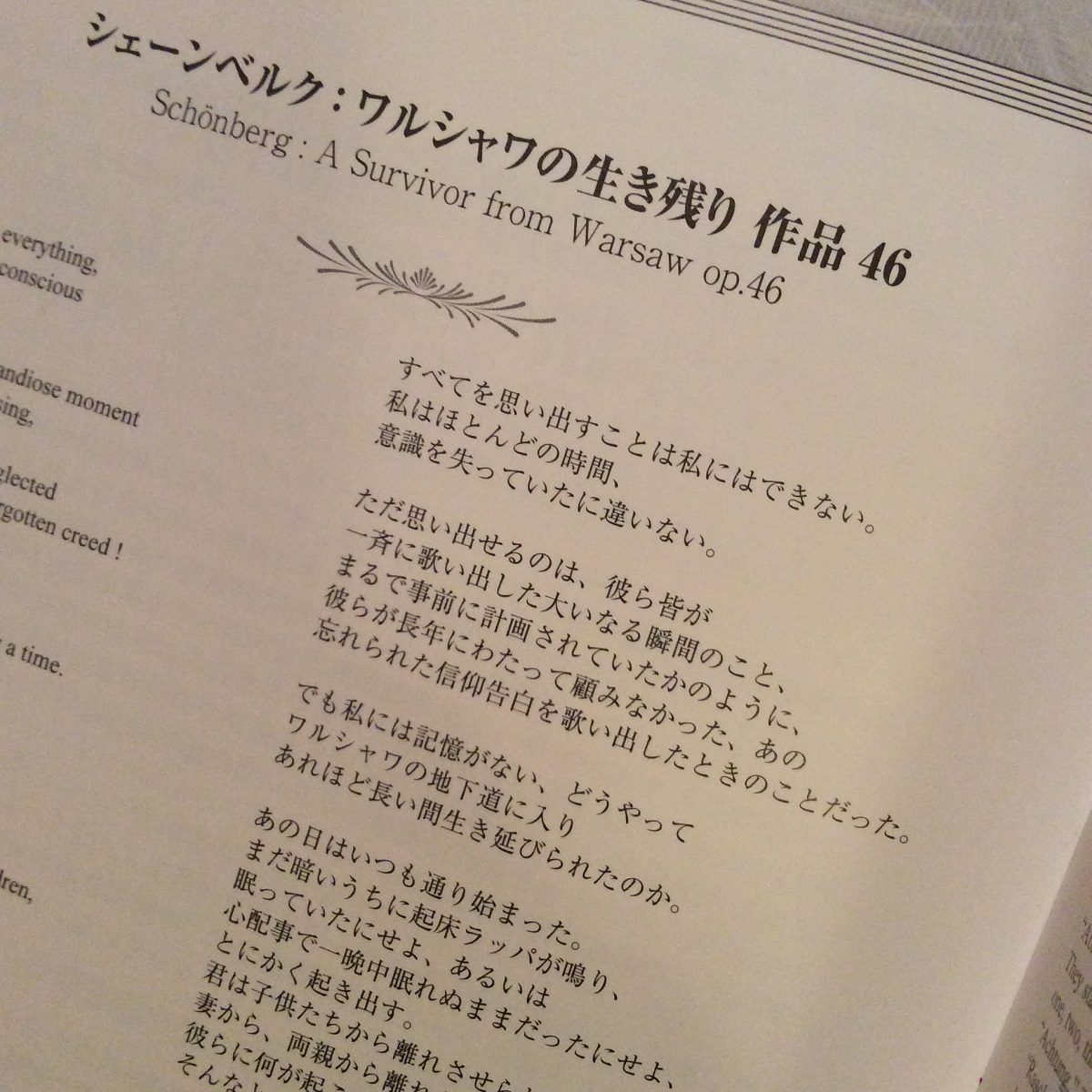第九をいつ聴いたか、思い出せない。
これまでに聴いたことがなかった…そうかも知れない。
聴いたことがない音楽を昨日、2018年12月27日に聴いた。
シェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」は、ものすごく前、たしか2000年にブリュッヘン指揮、クラウス・マリア・ブランダウア―の語りで聴いたことがある。その時は後半がクリスティーネ・シェーファーとイアン・ボストリッジの独唱でハイドンの「天地創造」という豪華なコンサートだったけれど…ほとんど覚えていない。
これは演奏会向けの作品だろうか、ということを思ったことは、なんとなく覚えている。 ブランダウアーはオーストリアを代表する名優だけれど、英語で叫んでいて、それだけでもトーンハレの雰囲気にまったくそぐわなかった上に、殴られて倒れこむ演技などをして客席に笑いが起こったように感じたことも、おぼろげに覚えている。
多分、ドイツ語だとそんな悲劇は起こらなかったかもしれないし、でもドイツ語でやるとナチ役のナチっぽさが失われるだろうし、そもそも…なんてことを考えてみて、この短さ(8分ほど)でいくら名優が頑張ったところで…グロテスク!大変な困難を伴った作品だというところで記憶がとまってしまっていた。
クーセヴィツキ―財団の依頼で書かれた「ワルシャワの生き残り」は、ボストン交響楽団で初演されるはずであった所を、アマチュアの市民と学生の混合オーケストラの指揮者であったカート・フレデリックがその初演を彼のオーケストラで行いたいとシェーンベルクに手紙を送り、シェーンベルクは了承した。
フレデリックは自身のアマチュアオーケストラと合唱団に集中的な稽古をつけたが、初演は予定より2カ月も遅れてしまった。1948年の11月初演、あっという間の8分間のあと、ショックで黙り込んだ聴衆に向けてフレデリックはもう一度演奏を繰り返し、2度目の演奏が終わった後、会場には雷のような拍手が沸き起こった。
戦後、という認識を、80年代初めには学校教育としてそれを共有していたことを、その時に子供であった自分は知っているけれど、アメリカではどうなのかという事は、知らない。しかし、90年代の「シンドラーのリスト」でさえ、自分にはかなりのショックであった。1948年のアメリカにおいては…
でも、戦後という認識が教育の段階を過ぎて完全にステレオタイプ、戦争はひどかった…、と化した今、「ワルシャワの生き残り」を上演することでは、おそらく何の事件も起きないし、おそらく客席の笑いさえも獲得できまい…という想像がまったく覆された凄まじい公演を、自分は昨日、2018年12月27日に京都で聴いたのだ。
19時、あまり大きくない編成のオーケストラと、これ以上もう一人も座れません、とまさしく寿司詰め状態に並んだ合唱団で舞台は埋まっていた。後ろのオルガン席はすべて空で、そこに大きく2本、日本語字幕のための表示装置が立っている。手元のパンフレットに対訳も載っているのに、贅沢な仕様だと思った。
「ワルシャワの生き残り」が始まった。バス歌手の語りは情熱にあふれ、しかし凛とした佇まいのまま、字幕付きの舞台劇が進行するのを、こんなにゆったりとした気分で観てていいのかなと思ったとたんに合唱団の男性パートが大声で歌い出してびっくりしたら、もう終わった。8分経ったのだ。
やっぱりあっけない…と思う間もなく、ほぼアタッカで第九の序奏が始まった、テンポは速い、空虚五度でも空気が揺るがない…そしてテーマの提示!
ダダー!
嘘だ、自分はあろうことか、なんと、笑いだしてしまった。
自分の書くことが、人の気に障るようなことがあっては申し訳ないけれど、それでないとこの演奏会が最終的に唯一無二のものとなったことを語ることが出来ないから、正直に書く。すみません。
笑ったといっても、声を出したわけでもない。ただ「ワルシャワ」の提示したグロテスクをベートーヴェンの哄笑に置き換えることなど、まったく想像していなかった事態に遭遇して、不謹慎とかなんとか、そんなことを考えるほどに、このプログラム考えた人は天才だと思った。
でも、その笑いもすぐにどこかに消えてしまった。
演奏が凄まじいのだ。
ワルシャワに重い意味を与えたまま、振り返らずに発進した第九は、それ自身のメッセージ性という啓蒙主義的な足枷も一緒に振り切ったらしく、ただひたすらに純器楽的な作品として、音楽のレトリックとしての疑問と解決を繰り返しながら突き進んで行った。
メッセージをはぎ取った第九からは、あの、のた打ち回るようなうねりが聴こえない。そんなものは、ワルシャワに置いて来たのだ。第九とは、こんなに恐ろしい作品なのかと思い、それをひたすらに演奏している指揮者とオーケストラも恐ろしいと思った。京都市交響楽団は、恐ろしい…。
解釈?
シューマンが心の中で聴いていた第九…ということが何度か頭を過ったけれど、それが解釈によるものか、もしくは作品がもともと所持しているものを見せてもらった結果なのか、それはわからない。ともかく、その場においてそれ以上を求めたいとはまったく思わず、ずっと聴いていたいと思って聴いていた。
そして第4楽章、各楽器によるひとしきりの無言劇、一、二、三、と彼らは繰り返す… だんだんに早くなっていく、それもいちいち凄い演奏なのが終わって一息ついたところで、それまでその存在をすっかり忘れていた字幕装置が輝きだした。
「おお友よ!」
記憶が瞬時にワルシャワに飛んだ。彼らはずっと、まだあそこにいたのだ。
そこから最後までを解説することは出来ない。
「ワルシャワの生き残り」が、第九を通して、 ある特定の個人の記憶ではなく、全人類、そのひとりひとりの記憶としてその場で蘇ったのを私たちは見たのであり、私たちはその場で跪いて、遠く世界を仰ぎ見た。そのような体験であった。
「ワルシャワ」の記憶が消し去られて無限の時間が流れたあとに、突如復活する装置としての字幕の存在。誰がこんなことを考えたのだろう…。こうしたことは、むしろ演劇作品で為され得ることかもしれないけれど、このような見事な展開の演劇を日本で観た記憶がない。
そして、その記憶は同じく下野氏指揮京響によるロームシアター開館記念の「フィデリオ」にも繋がっていく。ワルシャワ…フロレスタン。
すべてが繋がってしまって、そこにいる自分は、私という個人ではなくなってしまっていた。それは、音楽にせよ演劇にせよ、およそ劇場体験で引き起こされることの至上ではないだろうか。
脱帽しかない…。
平成が終わるということについて、考えることが多かったこの年末に、その感動に暫し放心状態となった素晴らしい公演でした。指揮の下野竜也さんと演奏家の皆さんにお礼が言いたいのと、京都市交響楽団がある京都に住んでいることへの感謝を込めて書きました。本当にありがとうございました。
・・・・・
2018年12月27日(木)7:00pm 開演
於:京都コンサートホール・大ホール
下野 竜也(常任首席客演指揮者)
京都市交響楽団
吉原 圭子(ソプラノ)
小林 由佳(メゾソプラノ)
小原 啓楼(テノール)
宮本 益光(バリトン)
京響コーラス
シェーンベルク:ワルシャワの生き残り op.46
ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調「合唱付」 op.125
https://www.kyoto-symphony.jp/concert/detail.php?id=714&y=2018&m=12